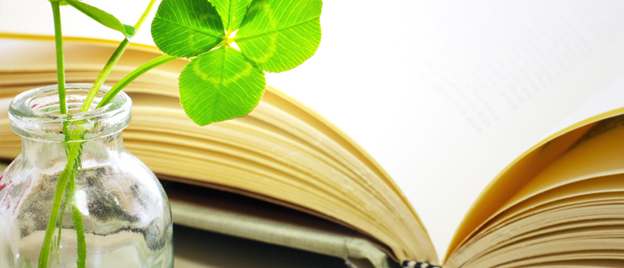教室近況
令和7年度は、8名の新入会員を迎えるという喜ばしいスタートとなりました。新たに加わった先生方は、早くもそれぞれの現場で活躍されております。今年度も新たに多くの仲間を迎えられたことは、教室にとって大きな活力となっております。一方で、中堅・ベテラン層には、「教える側」としての姿勢に加え、「若手が成長しやすい環境とは何か」を常に問い直す責任があると考えております。
令和5年春に始動した「思春期ルーム」プロジェクトは、昨年度末に思春期ルーム「Teens Terrace」の最終工事を終え、4月3日に完成披露会を開催いたしました。現在は、思春期の子どもたちにとっての憩いの場として機能しており、今後は思春期医療に関する新たな取り組みを発信する拠点となるはずです。
研究においては、八木久子講師を中心に、若手が主体的に研究へ取り組める体制づくりが着実に進んでおります。今年度も学位取得者、大学院進学者がおります。また、病理学教室や生体調節研究所、東北大学をはじめとする学外の研究機関とも連携が進み、日常診療と研究が好循環する体制が整いつつあります。さらに、国内留学として大阪大学や大阪精神医療センター、兵庫県立こども病院に赴く医師もいます。こども家庭庁に出向していた髙橋駿先生が大学に戻ります。こうした学外との交流は、教室のさらなる発展につながるものと期待しております。
臨床においては、石毛講師(外来)、井上貴博講師(NICU)、西田助教(小児病棟)、を中心に、バランスの取れた診療体制の構築が進められています。各診療グループでは専門医・指導医を配置し、臨床・研究・教育が有機的に連携する大学病院としての役割を果たしています。
教育では、原助教を中心に、学生の良さを引き出すことを重視した小児科実習を教室全体で実施しております。今年度も、医学部生を対象としたアンケートにおいて、小児科は「将来希望する診療科」として、内科に次ぐ第2位を維持しています。
群馬県においては今もなお、新生児医療や三次救急を担う医師の慢性的な不足、働き方改革の現場定着など、今なお取り組むべき課題も多く残されています。また、県立小児医療センターの大学隣接地への移転に関する具体的な計画も進行中です。少子化の進行とともに、県内の小児医療体制には抜本的な見直しが求められる時期を迎えております。私たち医会としても、滝沢教授のもと、変化に柔軟に対応するための具体的なビジョンの策定を進めております。
若手の入会が着実に進んでいる今こそ、教室全体がより一層活気づく好機です。その魅力を広く伝えることが、群馬県の小児医療をさらに充実させるために不可欠であり、医会の中心的な使命と考えております。小児科臨床・研究・教育・社会貢献に真摯に取り組み、疾病を抱える子どもとその家族と「喜怒哀楽を共にする」ことを厭わない若手医師の参画を、私たちはいつでも歓迎しています。ご関心のある方は、ぜひご連絡ください。
最後になりますが、当会の活動を支えてくださる医師会、同窓の先生方、地域の皆さまに心より感謝申し上げます。今後とも温かいご支援を賜れますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。
主な出来事
令和6年度
・9月14日 群馬大学小児科同窓会(前橋商工会議所会館)
・10月7日 関連部長会議
・10月28日 第2回医師の会(ハイブリッド開催)
・12月8日 第226回日本小児科学会群馬地方会講話会(前橋市)
・12月14日 忘年会(サンシャイン水族館)
・12月16日 第3回医師の会(ハイブリッド開催)
・1月20日 第4回医師の会(ハイブリッド開催)
・3月7日 臨時医師の会(ハイブリッド開催)
・3月9日 第227回日本小児科学会群馬地方会講話会(桐生市)
・3月28日 病棟送別会(アルバート邸,前橋市)
令和7年度
・4月 3日 群馬大学病院思春期ルーム「Teens Terrace」お披露目会
・4月 4日 お花見会(割烹 桃乃木,前橋市)
・5月 9日 新人歓迎会(ホテルラシーネ新前橋,前橋市)
・5月23日,6月20日 医学生と初期研修医対象群馬大学小児科説明会
・6月30日 関連部長会議
・7月 6日 第228回日本小児科学会群馬地方会講話会
・7月 7日 第1回医師の会(ハイブリッド開催)
・7月25日 暑気払いビアパーティ(ヴォレ・シーニュ,前橋市)
・8月22日・23日 第35回日本外来小児科学会年次集会(副実行委員長:井上佳也先生,札幌市)
・8月29日 初期研修医2年目対象群馬大学小児科説明会
・9月13日 群馬大学小児科同窓会(前橋商工会議所会館)

写真:群馬大学小児科新人歓迎会(5月9日)
令和7年度医会長 大津義晃(平成16年卒、平成18年入会)